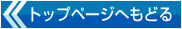京大呼吸器外科 京都大学医学部附属病院呼吸器外科
癌
- 肺癌の手術成績と予後因子の検討
- 非小細胞肺癌に対する術後補助化学療法
- 肺癌の発見および治療における分子マーカーに関する研究
- 肺癌の悪性度と血管新生との関連についての研究
- 肺癌における糖タンパクおよび糖鎖の発現と、その治療応用に関する基礎研究
- 肺癌の浸潤能・転移能に関する基礎研究
- ナノパーティクルを用いたDDS(drug delivery system)の肺癌治療への応用
1.肺癌の手術成績と予後因子の検討
肺癌は、男性において日本に於ける死亡原因のトップであり、女性においても次第にトップの座に近づきつつあります。手術手技或いは放射線照射法の進歩やプラチナ製剤、更には1990年代の新規抗癌剤の出現などにより、肺癌治療戦略は進歩を見せてはいますが、その5年生存率は未だ満足のいくものではありません。
特に放射線や抗癌剤に関しては、耐性の問題が治療成績の向上を妨げています。このような状況に新展開を与えると期待されているものに、分子標的治療があります。その標的分子は多岐にわたり、例えばアポトーシス関連分子、成長因子とその受容体、転写因子、接着因子、ストレス蛋白などがあげられます。私たちは、手術などで得られた臨床検体を使用して、予後因子の候補、或いは新規の標的分子の候補の発現を、遺伝子レベル、蛋白レベルで検索しています。
私たちは、既に予後因子として明らかになっている、Ki-67・腫瘍内血管密度・腫瘍内アポトーシス細胞比率、などが有用であることを検証するとともに、細胞表面糖蛋白糖鎖(Lewis Y, Polysialic acid)、アポトーシス関連分子(Caspase-3, p53過剰発現, p21)、血管新生因子(VEGF-A, -B, -C, -D, Matrix metalloproteinase-2)、接着因子(CD44, NCAM, L1-CAM)の発現と、腫瘍増殖及び予後との相関について報告してきました。京都大学医学研究科で発見され血管新生との関連が証明された、RECK遺伝子 (reversion-inducing-cysteine-rich protein with Kazal motifs) に関しては、非小細胞肺癌での発現例が予後良好であることを明らかにし、現在RECK遺伝子治療の開発研究を進めています。
今後ともこのような治療標的分子の検証を継続して行い、分子標的治療及びテーラーメイド化学療法の進歩に寄与することを、私たちのグループの目標としています。
2.人工ニュ−ロンネットワ−クを用いた 機能的電気刺激による呼吸と咳の再生と協調
化学療法、放射線療法が治療の主体となる小細胞肺癌に対して、非小細胞肺癌(腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌等)では、切除可能な場合は手術療法が第一選択となります。通常はI期、II期、およびIIIA期の一部がその対象です。しかしながら、その手術成績(手術後の生存率)は決して満足できるものではなく、私たちはその向上をめざした取り組みを行ってきました。
非小細胞肺癌の手術成績を左右するのは、手術後高頻度に生じる遠隔転移での再発の制御であり、故に全身化学療法が重要となってきます。そこで私たちは、経口抗癌剤のUFTに注目し、1980年代から検討を行ってきました。UFTは、抗癌剤5-FUのプロドラッグであるテガフール(FT)に5-FUの分解酵素阻害剤であるUracilを配合したもので、biochemical modulation(BCM;抗腫瘍効果を持つ薬剤に別の薬剤を追加することで、その抗腫瘍効果を高める)という概念に基づいた薬剤です。当教室を中心として組織された、「西日本肺癌手術の補助化学療法研究会(WJSG)」では、手術成績の向上をめざした取り組みとして、UFTの術後補助化学療法としての有効性を検討しました。そして、同研究会第2次研究での臨床試験で、世界で初めてその有効性を示しました。また、その結果の詳しい解析から、早期の手術症例での有効性が示唆され、I期腺癌症例に絞った大規模な臨床試験(999例をUFT服用群と非服用群に無作為化割付)で、その有効性が改めて確認されています(“経口内服薬(UFT)で肺癌手術成績が向上!”を参照)。これらの結果から、先頃改訂された「EBMの手法による肺癌診療ガイドライン」では、UFTによる術後補助化学療法は、早期症例に対して“行うよう勧められる”とされ、当教室の取り組みが結実しました。
その他、私たちは、UFTの術後補助化学療法としての効果を予測する因子の検討も行ってきました。その一つとして、5-FUの分解酵素の一つである dihydropyrimidine dehydrogenase(DPD)の腫瘍内での発現をレトロスペクティブに検討し、DPDの発現の強弱が、UFTの術後補助化学療法としての効果に関連する可能性について報告しました。
現在、当教室では、同じく経口抗癌剤であるTS-1などを用いた臨床研究を進めるべく、準備を行っています。
3.肺癌の発見および治療における分子マーカーに関する研究
肺癌治療として一般的に行なわれているものとして、外科手術、抗癌剤治療(化学療法)、放射線療法、および近年臨床応用が進んでいる分子標的治療があります。これらの治療法のうち、抗癌剤治療、放射線療法、分子標的治療については、個々の肺癌の分子生物学的特性を調べることによって、どのような治療法、治療薬が最も有効かを予測し、それによって個々の患者さんごとに治療法を最適化する、いわゆるテイラーメイド治療を実現するための研究が、盛んに行なわれています。
私たちは、上皮成長因子受容体(EGFR)の阻害薬であるゲフィチニブの効果を予測する、EGFR遺伝子の変異を、研究室で迅速に検出する方法を開発し、既に臨床応用しています。更に、肺癌の治療に使用される各種抗癌剤の効果を予測することを目標に、様々な分子マーカー(目印)の同定と、その治療への応用に関する研究を行っています。
また悪性腫瘍の治療において、発病や再発の早期発見はきわめて重要です。私たちは、癌に特異的に発現する遺伝子を分子マーカーとして利用し、癌の発病や再発を効率的に監視できる可能性を探索しています。
3.肺癌の発見および治療における分子マーカーに関する研究
肺癌治療として一般的に行なわれているものとして、外科手術、抗癌剤治療(化学療法)、放射線療法、および近年臨床応用が進んでいる分子標的治療があります。これらの治療法のうち、抗癌剤治療、放射線療法、分子標的治療については、個々の肺癌の分子生物学的特性を調べることによって、どのような治療法、治療薬が最も有効かを予測し、それによって個々の患者さんごとに治療法を最適化する、いわゆるテイラーメイド治療を実現するための研究が、盛んに行なわれています。
私たちは、上皮成長因子受容体(EGFR)の阻害薬であるゲフィチニブの効果を予測する、EGFR遺伝子の変異を、研究室で迅速に検出する方法を開発し、既に臨床応用しています。更に、肺癌の治療に使用される各種抗癌剤の効果を予測することを目標に、様々な分子マーカー(目印)の同定と、その治療への応用に関する研究を行っています。
また悪性腫瘍の治療において、発病や再発の早期発見はきわめて重要です。私たちは、癌に特異的に発現する遺伝子を分子マーカーとして利用し、癌の発病や再発を効率的に監視できる可能性を探索しています。
4.肺癌の悪性度と血管新生との関連についての研究
血管新生は、各種増殖性炎症、創傷治癒過程、発生、性周期における子宮内膜増殖などの際に見られる現象ですが、腫瘍増殖にとっても重要な反応のひとつです。腫瘍による血管新生刺激に始まり、基底膜の分解、血管内皮細胞の遊走、血管内皮細胞の増殖を経て管腔形成に至る、血管新生の複雑なプロセスは、様々な機序によって調節されており、多くの研究者によって研究されてきています。私たちは、肺癌における血管新生の重要性を評価するため、これまでに以下のような因子について検討を行ってきました。
抗CD105抗体による腫瘍内血管密度:CD105は、血管内皮のマーカーのひとつですが、CD34が血管内皮共通のマーカー(pan- endothelial marker)であるのに対し、CD105は新生血管(newly forming vessel)に特異的なマーカーです。私たちは、抗CD105抗体を用いて腫瘍内血管密度(Intratumoral microvessel density; IMVD)を測定し、IMVDの高い症例は有意に予後不良であることを報告しました。
VEGF-C, Angiopoietin-2:いずれも血管新生因子のひとつであり、腫瘍細胞におけるVEGF-C高発現は、有意な予後不良因子であることを報告しました。また、Angiopoietin-2は、VEGFと関連して血管新生を促進する因子であり、これも予後に関連していることがわかりました。
Carbonyl reductase(CBR):細胞内還元酵素の一種であり、プロスタグランジン、ステロイドホルモン、キニン、アントラサイクリン系抗生物質などをその基質とします。VEGFやMatrix metalloproteinase(MMP)を誘導して血管新生を促進する働きがあり、アポトーシス抑制などの作用も報告されています。私たちは、CBR遺伝子のmRNA発現量とCD105-IMVDとの間に有意な相関があることを示し、CBR遺伝子の発現が低い症例は予後不良であることを報告しました。
この他、経口抗癌剤UFTの効果と、血管新生との関連についても検討しました。その結果、I期腺癌手術症例において、IMVD高値やVEGF高発現を示すなどの血管新生が盛んな症例群では、UFT投与が予後を改善する可能性のあることがわかりました。私たちは、引き続き様々な観点から、肺癌における血管新生についての研究を行っています。
5.肺癌における糖タンパクおよび糖鎖の発現と、その治療応用に関する基礎研究
肺癌は、リンパ節や全身への転移など、進行した状態で発見されることが多く、極めて予後不良の疾患です。また、転移はなく手術で完全に切除したと判断されても、すでに目に見えない転移が存在し、手術後に遠隔転移で再発することも少なくありません。そこで、転移のメカニズムを解明し、それを制御する治療法を開発することが、肺癌研究の大きな目標となっています。
癌細胞の細胞膜表面には、さまざまなタンパク、糖鎖、糖タンパクが存在し、それらの機能異常が癌の進展や増殖に深く関わっていることが明らかになっていますが、糖鎖の機能については、未だ不明な点が多く残されています。そのなかで、シアル酸がα2−8結合して直鎖状となったポリシアル酸(PSA)は、神経細胞のNCAM(neural cell adhesion molecule)に結合する糖鎖で、胎生期の組織で多く発現し、神経突起の伸張などに関わる一方、Wilms’腫瘍、神経芽細胞腫、肺小細胞癌などいくつかの癌細胞での発現が報告され、細胞の接着能を落とすことから、転移との関連が示唆されてきました。
これまでの私たちの研究では、非小細胞肺癌においてもPSAの発現が見られ、その頻度は病理病期I期(20.8%)で低く、IV期(76.8%)で高いこと、リンパ節転移や遠隔転移と相関していることが分かっています。また、PSA合成酵素の一つであるSTX遺伝子は、癌組織のみで発現しており、その発現頻度が癌の進行度と相関していることを明らかにしました。更に、病理病期I期の完全切除された非小細胞肺癌症例でも、PSA発現症例は、PSA陰性症例に比べて有意に予後が悪いことを報告してきました。以上の結果より、PSAを標的分子として、その働きを制御することで肺癌の転移や再発を抑制することを目標とし、現在研究をすすめています。
粘膜上皮細胞表面に豊富に存在し、細胞表面の潤滑性を保つ膜タンパクであるMUC1は、長いコアタンパクに糖鎖を大量に付加された糖タンパクですが、癌細胞では過剰発現や糖鎖の減少が報告され、癌細胞内の増殖シグナルとの関連、あるいは細胞間接着や細胞基質間接着を阻害する作用などから、癌の増殖・転移に深く関わるとされてきました。また、MUC1のコアタンパクには、抗腫瘍免疫活性を賦活する腫瘍抗原としての働きがあり、抗腫瘍免疫治療の標的分子として注目されています。私たちは、非小細胞肺癌でのMUC1の発現様式に着目し、MUC1が細胞質内に広がったり、細胞表面全体に発現する場合は、特に腺癌において分化度が悪く、予後も悪いことを明らかにしました。このような症例に対しては、術後補助療法を強化したり、MUC1を標的とした免疫治療を考慮したりすることを検討しています。また、共同研究で、血液中のMUC1由来の糖鎖の解析も計画しています。
6.肺癌の浸潤能・転移能に関する基礎研究
癌の浸潤,転移のメカニズムは複雑で,きわめて多くの因子が関連しています。癌細胞は転移する際に,まず周囲組織へ浸潤し,次いで血管内に入り、血流にのって他の臓器に達し,さらに血管外に出て、そこで再び増殖するという過程を経るとされています。そのためには、まず基底膜や細胞間組織などの細胞外マトリックスを破壊する必要があります。
近年注目されているマトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)は,癌が細胞外マトリックスを破壊し浸潤する際に誘導・分泌される物質で,MMPの阻害は浸潤・転移の制御においてきわめて重要と考えられています。私たちは、切除肺癌組織において、MMPファミリーのひとつであるMMP-2の腫瘍間質での発現が,予後と関係することを報告しました。また、私たちが研究対象としているRECKは,共同研究者である京都大学医学研究科分子腫瘍学の野田亮教授らが同定した新規遺伝子で,MMPの働きを阻害する因子です。私たちは、RECKが肺癌組織において、腫瘍の転移に重要な血管新生を抑制すること,また、 RECKの発現の高い症例が予後良好であることを確認し、報告しました。現在私たちは、RECK遺伝子を用いた遺伝子治療の可能性を探るため、基礎研究を行っています。
また、癌の浸潤転移には,癌細胞自体の運動能が関与しています。Arf6という蛋白質は、癌細胞の運動に直接関与し、特に癌細胞の血管内への浸潤、他臓器に達した後の血管外への浸潤に、深く関与すると報告されています。私たちは、共同研究者である大阪バイオサイエンス研究所・第一研究部と協力し、Arf6 の活性化を調節する分子であるAMAP1の働きを基礎実験で検証し、肺癌細胞でもAMAP1→Arf6が癌細胞の浸潤に関与すること、および、それらの阻害により癌細胞の浸潤自体も抑制できることを示しました。将来的にはこれらの知見を肺癌治療に応用し、癌の浸潤転移を制御することを目標として、現在更に基礎実験を重ねています。
7.ナノパーティクルを用いたDDS(drug delivery system)の肺癌治療への応用
ここ数年、世界中で高い注目を浴びているナノテクノロジーは、先端医療との融合により、ナノメディスンという新しい技術領域へと進歩しています。なかでも、ナノサイズの微粒子キャリア(ナノパーティクル)を用いたDDS(drug delivery system)については、盛んに研究開発が行われています。我々は、京都大学工学研究科にて開発された葉酸コレステロールプルラン(FA-CHP)というナノパーティクルに注目して研究を行っています。
FA-CHPは、粒子の表面に葉酸を付加して、細胞内に取り込まれやすいようにデザインされたナノパーティクルであり、内包された薬物などを効率よく細胞内に送り込むことができます。増殖の盛んな癌細胞では、葉酸代謝回転がはやいため、FA-CHPを介して癌細胞に選択的に薬剤をとりこませることができるのではないか、と考えられます。私たちは、FA-CHPの肺癌治療への応用によって、より少ない薬剤の量で治療効果を高め、副作用を軽減することが可能かどうかを検討するため、肺癌細胞株やマウスの肺癌モデルを用いて基礎研究を行っています。